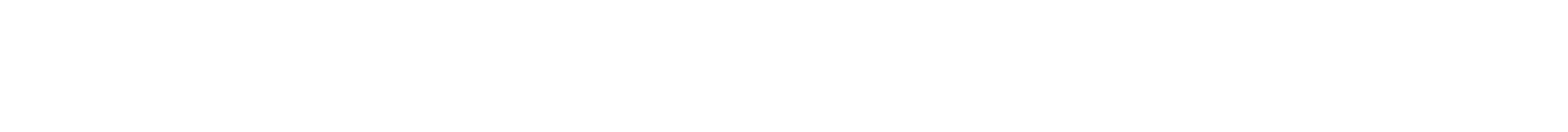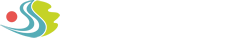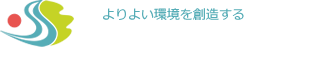作業環境測定結果が第3管理区分になったら?
作業環境測定結果が第3管理区分になった場合、次のことが義務付けられます。
- 作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、外部の作業環境管理専門家からの意見を聴くこと。
- 作業環境管理専門家の意見より、作業環境の改善が可能と判断した場合、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、その措置の効果を確認するための濃度測定行い、その結果を評価すること。
作業環境管理専門家の要件は?
- 化学物質管理専門家の要件に該当する者
- 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに合格した者に限る。) 又は労働安全コンサルタント(試験の区分が化学であるものに合格した者に限る。)で あって、3年以上化学物質又は粉じんの管理に係る業務に従事した経験を有する者
- 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者
- 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験 (試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、3 年以上労働災害防止団体法第11 条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者
- 6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者
- 4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、(公社)日本作業環境測定協会が実施する研修または講習のうち、同協会が化学物質管理専門家の業務実施に当たり、受講することが適当と定めたものを全て修了した者
- オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者
作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務
作業環境管理専門家が、「作業環境の改善は困難と判断した場合」または「作業環境の改善措置を講じた上で、その措置の効果を確認するための濃度測定の結果、なお第3管理区分に区分された場合」、事業者は、次の措置を講じることが義務付けられます。
- 個人サンプリング測定等により対象物質の濃度測定を行い、測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。(フィットテスト)
- 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。
- 上記1の作業環境管理専門家の意見の概要並びに②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
- 1~3での措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署長に提出すること。
作業環境評価結果が改善するまではどうしたらよいの?
- 6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
- 1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。
作業環境管理専門家に意見を聴きたいときはどうしたらよいの?
フィットテストって何?
面体を有する呼吸用保護具は、顔面で気密を形成する方式のものですので、これらと着用者の顔との密着性が不十分だと環境中の有害物が漏れこむ原因となります。フィットテストは、この密着性(フィット)を評価する方法です。
フィットテストの主要な目的は、使用させている(又は使用させようとしている)面体の製品モデル及びサイズが着用者に適したものであるか否かを調べることです。もし不合格となった場合は、サイズの異なるもの、製品モデルが異なるもの、異なるメーカーの製品まで枠を広げ、合格する面体を探さなければなりません。
このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。
どんな時にフィットテストが必要なの?
主に以下3つのケースで、フィットテストを実施する義務があります。
- 屋内作業場において継続して金属アーク溶接等作業を行う作業者
(特定化学物質障害予防規則 第38条の21) - 特別則に基づく作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分され、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合及び改善
措置効果確認測定において、なお第3管理区分に区分された場合の措置として呼吸用保護具を使用する場合
(有機則第28条の3の2、特化則第36条の3の2、粉じん則第26条の3の2、鉛則第52条の3の2) - リスクアセスメントに基づくリスク低減措置として呼吸用保護具を労働者に使用させる事業場
(労働安全衛生規則第577条の2)
このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。
どれくらいの頻度でやればいいの?
年1回、定期的に実施しなければなりません。記録は3年間保管となります。保存は紙でも電子媒体でも構いません。
また、着用者に次のような変化があった場合、面体の密着性に影響を与える可能性がありますので、フィットテストを実施しなければなりません。
- 体重の著しい変化
- 面体が密着する部分の傷跡、手術などによる変化
- 歯の変化
- 着用者の不快感
このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。
フィットテストの発注や準備はなにが必要なの?
使用しているマスクのメーカー及び型式をお伝えください。
専用アダプターが必要な面体があり、実施まで2週間ほど準備期間をいただく場合もあります。
テスト当日は、フィットテストに使用する部屋として打合せ室や休憩室などの、比較的清潔な場所をご準備ください。
テスト前にはマスクを清潔な状態としてください。弁が汚れにより作動していなかったり、締め紐の劣化、弁やパッキンが外れているケースもあります。
※新品マスクでのテストをお勧めします。
またテストを行うマスクが不合格になる場合を想定して、複数種類のマスクの準備があると、なお良いです。
このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。
フィットテストの定量と定性とは?またどちらが良いの?
定量的フィットテストは、面体の接顔部からの漏れ量を、測定装置を用いて数値として計測する方法です。長所として、テスト時間が短いこと(短縮法を選択可能)やリアルタイムで漏れ確認ができる点があります。
定性的フィットテストは被験者の感覚(味覚や嗅覚)により、面体を着用しているときに試験物質を感じるか否かを調べる方法です。
長所として感覚で判定するため、マスクの効果を実感できる点があります。
どちらの方法もJIS T 8150:2021 に記載されており、どちらを選択しても構いません。
このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。
テスト時間はどれくらいなの?
1人当たり、定量的フィットテストの場合は最短で約5分ほど、定性的フィットテストは最短で約10分となります。
このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。
化学物質管理が見直されたのはなぜ?
国内で使用される化学物質は7万種類を超えていますが、規制されているものは石綿等管理使用が困難な8物質と特化則や有機則等の個別規則に概要する123物質しかありません。
そうした中で、化学物質による労働災害は年間450件程度で推移し、その8割が規制されていない化学物質の使用によるものです。
労働災害が発生して国が規制をすると、規制のない代替物質を利用し十分な対策を講じないことで労働災害が発生するような悪循環となっています。
こうしたことから、国がリスク評価に基づく個別管理から、事業者が取り扱う化学物質を調査(リスクアセスメント)し、ばく露を最小限にする自律型管理に見直されました。